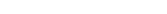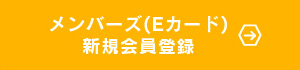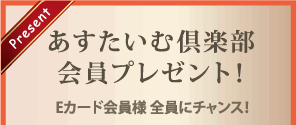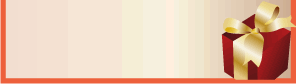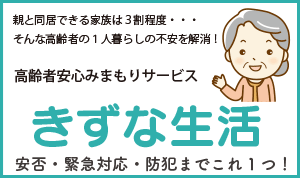歴史TOP > 第14回 山の辺の道がとおるまち・天理市を歩く(奈良県天理市)
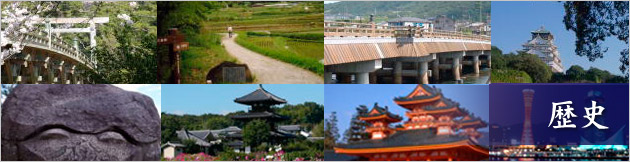
第14回 山の辺の道がとおるまち・天理市を歩く(奈良県天理市)
山の辺の道の出発点・石上神宮

荘厳な雰囲気がただよう石上神宮
天理駅から徒歩約20分、世界各地の生活文化資料・考古美術資料を研究・展示する天理参考館があります。そこからさらに歩いて約15分。県道51号を渡ると石上神宮の参道へと続きます。
車の行き交う県道から、社の境内に入ると雰囲気がガラッと変わります。そこには、悠然と闊歩する多数の鶏が目を引き、何かしら厳かな雰囲気が漂います。
「石上布留の神杉神さびし 恋をも吾はさらにするかも」と、柿本人麻呂が万葉集にうたっている石上神宮は、現存する日本最古の拝殿をもち、百済王が倭王に献じたのではといわれる七支刀や素盞鳴尊が八岐大蛇を退治したと伝わる天羽斬剣など、神庫には数多くの武器が収められています。
神宮の前からは、奈良盆地の東に連なる美しい青垣の山裾を縫うように「山の辺の道」が続いています。
花の寺・長岳寺

花の寺・長岳寺

天理市トレイルセンター
長岳寺の近くにあり、歴史街道のiセンターでもある天理市トレイルセンターは、休憩所にもなっており、シャワーなどの施設もありますので、山の辺の道散策の拠点施設として利用してください。
万葉歌碑をたどる

山の辺の道に建つ万葉歌碑
衾道とはこの辺りの地名で、引手の山とは東にそびえる龍王山ではないかと考えられています。
この山には、6~7世紀にかけて造られた奈良県最大級の群集墳である龍王山古墳群や、中世の豪族、十市氏が築いた大和を代表する山城・龍王山城跡があります。最も高い山頂付近に南城跡、その北尾根に北城跡など、あちらこちらに土塁や竪堀の跡が残ります。また山頂からの眺めは素晴らしく、大和三山など奈良盆地を一望することができます。
卑弥呼のロマンを感じる黒塚古墳

黒塚古墳
奈良市の春日山麓から大和盆地の東、天理を経て桜井の金屋にいたる約26キロの自然のままの山の辺の道には、今も、記紀・万葉集ゆかりの地名や伝説が残り、神さびた社や古寺、古墳などが点在しています。
地元のボランティアガイドの方に案内をお願いし、話をうかがいながら散策すると、また違って風景が見えてきます。
天理市山の辺の道ボランティアガイドの会
■周辺の見所
大和神社
天理市・上ツ道沿いに建つ大和神社は、伊勢神宮と並ぶ最古の神社で、延喜式には「大和坐大国魂神社」と記されています。境内には、戦艦大和の鎮魂碑があります。戦艦大和の艦長は出艦前に大和神社に詣で、守護神として艦上には大和神社の分霊がまつられていたとか。
9月23日には、江戸時代、干ばつに苦しむ農民が大和神社に雨乞いを行い、願いが成就し豊作となり、感謝の気持ちを踊りで奉納したのが始まりと言われる五穀豊穣を祈る秋の大祭「紅幣踊り」(天理市無形文化財)がおこなわれます。

最古の神社・大和神社
戦艦大和の鎮魂碑
天理市・上ツ道沿いに建つ大和神社は、伊勢神宮と並ぶ最古の神社で、延喜式には「大和坐大国魂神社」と記されています。境内には、戦艦大和の鎮魂碑があります。戦艦大和の艦長は出艦前に大和神社に詣で、守護神として艦上には大和神社の分霊がまつられていたとか。
9月23日には、江戸時代、干ばつに苦しむ農民が大和神社に雨乞いを行い、願いが成就し豊作となり、感謝の気持ちを踊りで奉納したのが始まりと言われる五穀豊穣を祈る秋の大祭「紅幣踊り」(天理市無形文化財)がおこなわれます。

最古の神社・大和神社

戦艦大和の鎮魂碑
■天理市の情報はこちらから
天理市観光協会
http://kanko-tenri.jp/
http://kanko-tenri.jp/
■天理市へのアクセス
歴史街道のイベント
歴史街道スタンプラリー2015
開催中〜平成28年5月31日(火)
「歴史街道」は日本の歴史を時代の順にたどることのできる300キロのメインルートと、それぞれの地域を歴史テーマで結ぶ3つのネットワークから構成されています。
スタンプラリーは、この「歴史街道」を楽しく巡りながら、寺社や博物館などに設置されているスタンプを集めるイベントです。主要駅設置のパンフレットのMAPをご参照の上、スタンプを集めてください。
●歴史街道各地に設置の30種類のスタンプを6種類集めると漏れなく景品をプレゼント
●ご応募いただいた中から、歴史街道各地の物産を抽選でプレゼント
●Wチャンスとして、歴史街道エリアにあるホテル、旅館(計6施設)の宿泊券を抽選でプレゼント
詳しくは歴史街道ホームページ http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/stamp/または主要駅設置のパンフレットをご覧ください。
●ご応募いただいた中から、歴史街道各地の物産を抽選でプレゼント
●Wチャンスとして、歴史街道エリアにあるホテル、旅館(計6施設)の宿泊券を抽選でプレゼント
詳しくは歴史街道ホームページ http://www.rekishikaido.gr.jp/time-trip/stamp/または主要駅設置のパンフレットをご覧ください。
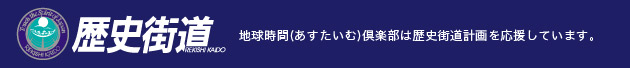
あなたも「歴史街道」の応援団に!
10月1日から「入会金無料キャンペーン」を実施しています。
歴史街道倶楽部は、「歴史街道計画」の推進を応援し、歴史文化に親しみたいという方のための倶楽部です。ご入会いただきますと、歴史の舞台を旅するオリジナルイベント「歴史のまちウォーク」に参加できるほか、四季折々の情報を満載した会員誌「歴史の旅人」がお手元に届きます。
歴史街道倶楽部では、もっと多くの方にご参加いただき、日本の歴史文化の良さにふれていただけるよう、10月1日から来年2月28日までの期間「入会金 無料キャンペーン」実施しています。
また、今回は、あわせて特別賛助会員(年会費10,000円)も募集しています。
この機会に是非、歴史街道倶楽部にご入会ください!
■年会費:3,000円(特別賛助会員は10,000円)
■入会金:1,000円 ※キャンペーン期間中は無料
■お問合せ先:歴史街道倶楽部事務局 TEL:06-6223-7182(平日10:00~17:00)
詳細、資料請求はコチラのバナーをクリック!▼
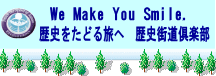
- 第85回 歴史街道「かつての伊勢の台所 河崎」
- 第84回 歴史街道「朝来市生野銀山」
- 第83回 歴史街道「古代史のまち 京丹後市」
- 第82回 歴史街道「近代ゾーン」
- 第81回 歴史街道「戦国・江戸時代ゾーン」
歴史TOP > 第14回 山の辺の道がとおるまち・天理市を歩く(奈良県天理市)

このサイトは、プライバシー保護のため、
SSL暗号化通信を採用(導入)しています。
SSL推奨ブラウザについて