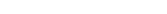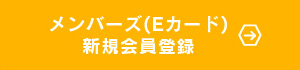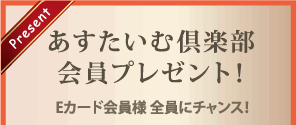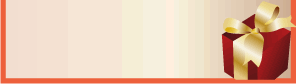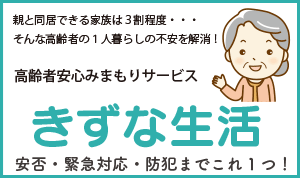歴史TOP > 第1回 陶芸のさと 信楽(滋賀県甲賀市信楽町)
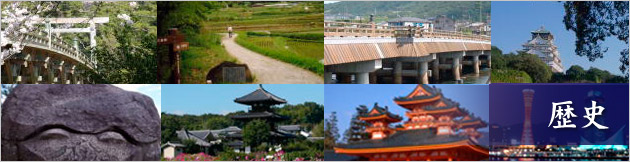
第1回 陶芸のさと 信楽(滋賀県甲賀市信楽町)
信楽を訪ねたら、車でもまずは信楽駅へ
※信楽駅から徒歩2分の甲賀市信楽地域市民センター(旧信楽支所)に駐車場有

店先に並ぶタヌキたち
途中、道の左右には陶器のお店が。もちろん、様々な信楽焼きを販売していますが、なんといっても圧巻は「たぬき」。狸の顔は時代とともに変わり、昔はより自然のたぬきに近く、ちょっと細面の怖い顔。今は、丸みのある、小首をかしげた愛嬌たっぷりのタヌキが主流とか。軒先にならぶタヌキの表情の違いを観察するのも楽しいものです。
歴史街道iセンターでもある信楽伝統産業会館は、鎌倉時代のやきものから近世のものまで、ひと目でわかる信楽焼の歴史を展示するほか、企画展示も随時開催しています。観光案内の拠点として信楽の情報のみならず歴史街道各地の情報も発信しているので、散策の前に是非立ち寄りたい施設です。

信楽焼たぬき
“幼などき 集めしからに懐かしも しがらき焼の狸をみれば”
昭和天皇が信楽を行幸された時、陛下を歓迎するのに里人だけでは寂しいので、国旗をもったタヌキの置物を道路に並べ歓迎したとか。この歌は、昭和天皇がそのタヌキを見て、幼児期にタヌキをコレクションされていたことを思い出されて歌ったもの。それが新聞などで報道され、信楽焼のタヌキが有名になったとか。
信楽焼は日本六古窯のひとつで、その歴史は古く中世末期から壺、甕、擂鉢などの焼き物が始められ、昭和の時代には火鉢の全国シェア80%を占めていたそうですが、タヌキの歴史は意外と新しいものでした。

何気なく軒先に置かれた立匣鉢

登り窯ギャラリー「Ogawa」

登り窯の内部まで見学できる
この辺りでは、陶芸作家のちょっとした遊び心を見る事ができます。
陶器のペンギンがあたかも散歩をしているかのように置かれていたり、壺などのちょっとした作品がなにげなく、道端におかれていたり。今はもう使われなくなった登り窯の跡も風景としてまちの中に溶け込んでいました。
ちょっと風変わりなタヌキの置物が入口に置かれた「谷寛窯 ギャラリー陶ほうざん」は、明治時代の師範学校の講堂を移築し作業場として活用していたものを現在はギャラリーとして用い、置物から日常使いの食器まで、さまざまな焼き物が置かれています。
他にも見学やショッピング、陶芸体験などができる窯元もあります(事前予約が必要なところもあります)。ぶらり、「陶芸のさと」めぐりはいかがですか。
■周辺の見どころ
滋賀県立陶芸の森 http://www.sccp.jp/
やきもの専門の美術館「陶芸館」をはじめ「信楽産業展示館」、「創作研修館」の三つの施設が、
約100点もの陶芸作品が展示されている公園内に建っています。
やきもの専門の美術館「陶芸館」をはじめ「信楽産業展示館」、「創作研修館」の三つの施設が、
約100点もの陶芸作品が展示されている公園内に建っています。
■信楽の観光情報はこちらから
ほっとする信楽 http://www.e-shigaraki.org/ (信楽町観光協会)
■信楽へのアクセス
信楽は新名神高速道路の信楽ICからすぐ。京阪神、名古屋方面からも便利です。
◇新名神高速道路「信楽I.C.」から約10分
名阪国道「壬生野I.C.」から約30分
ゆっくりのんびりと電車で行きたい方は、信楽高原鐵道で。平成25年の台風の被害で長らく運休が続いていましたが、平成26年秋、1年2か月ぶりに運転が再開されています。
◇JR草津駅から約1時間
JR琵琶湖線「草津駅」経由、草津駅着「貴生川駅」乗り換え、
SKR信楽高原鐵道「信楽駅」下車
◇新名神高速道路「信楽I.C.」から約10分
名阪国道「壬生野I.C.」から約30分
ゆっくりのんびりと電車で行きたい方は、信楽高原鐵道で。平成25年の台風の被害で長らく運休が続いていましたが、平成26年秋、1年2か月ぶりに運転が再開されています。
◇JR草津駅から約1時間
JR琵琶湖線「草津駅」経由、草津駅着「貴生川駅」乗り換え、
SKR信楽高原鐵道「信楽駅」下車
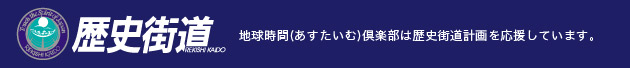
あなたも「歴史街道」の応援団に!
10月1日から「入会金無料キャンペーン」を実施しています。
歴史街道倶楽部は、「歴史街道計画」の推進を応援し、歴史文化に親しみたいという方のための倶楽部です。ご入会いただきますと、歴史の舞台を旅するオリジナルイベント「歴史のまちウォーク」に参加できるほか、四季折々の情報を満載した会員誌「歴史の旅人」がお手元に届きます。
歴史街道倶楽部では、もっと多くの方にご参加いただき、日本の歴史文化の良さにふれていただけるよう、10月1日から来年2月28日までの期間「入会金 無料キャンペーン」実施しています。
また、今回は、あわせて特別賛助会員(年会費10,000円)も募集しています。
この機会に是非、歴史街道倶楽部にご入会ください!
■年会費:3,000円(特別賛助会員は10,000円)
■入会金:1,000円 ※キャンペーン期間中は無料
■お問合せ先:歴史街道倶楽部事務局 TEL:06-6223-7182(平日10:00~17:00)
詳細、資料請求はコチラのバナーをクリック!▼
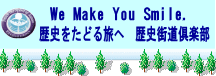
- 第85回 歴史街道「かつての伊勢の台所 河崎」
- 第84回 歴史街道「朝来市生野銀山」
- 第83回 歴史街道「古代史のまち 京丹後市」
- 第82回 歴史街道「近代ゾーン」
- 第81回 歴史街道「戦国・江戸時代ゾーン」
歴史TOP > 第1回 陶芸のさと 信楽(滋賀県甲賀市信楽町)

このサイトは、プライバシー保護のため、
SSL暗号化通信を採用(導入)しています。
SSL推奨ブラウザについて