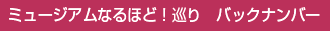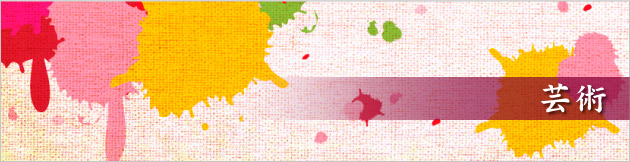
ミュージアムなるほど!巡り
今までのミュージアム関連の鑑賞歴、接触人脈そして現在のミュージアム支援機会を生かして、様々な視点によるミュージアムの魅力等をご紹介しながら、アクティブシニアの皆様のゆとり生活設計支援ができれば幸いです。
- コラム一覧
- 第三十回 ますます魅力が深化する
「ミュージアムぐるっとパス・関西2015」 - 第三十一回 京都・祇園の華やいだ空間に、
フェルメール「光の王国展」がとろける。 - 第三十二回 何度でも、自由に、待たずに
「関西ミュージアム-3日間無料入場パス18-」 - < 前へ
- 次へ >
第三十一回 京都・祇園の華やいだ空間に、フェルメール「光の王国展」がとろける。

京都・祇園「光の王国展」チラシ フェルメール「光の王国展」を由緒ある、ゆったりとした和室で開催したのは、これが初めてである。しかも、京都・祇園にある甲部歌舞練場「八坂倶楽部」を利用して、なんと2ヶ月間(2015年7月1日~8月31日)に及ぶ長い期間である。お蔭様で来場者は土曜・日曜を中心に尻上がりに増加しているとの報告を聞いた。この夏、京都独特のうだるような暑さの中での展覧会ではあるが、2階で同時に開催中の「舞妓物語展」との併設の告知が祇園・花見小路を闊歩するたくさんの中国人や白人の眼にとまり、国際色豊かな展覧会へと拡大している。
そもそも、この京都祇園の甲部歌舞練場「八坂倶楽部」の建物は大正天皇の御即位の儀式の時に饗宴の場として建てられ、賑々しく利用された所だと聞く。現在では毎年一度だけ4月に開催される華麗な「都をどり」の時に、黒紋付の襟を返した芸妓さんがお茶を点てる姿が目の前で拝見でき、お茶席での「おもてなし」の会所として知る人ぞ知る価値のある場所である。また、お土産として持ち帰る「団子皿」を集めるのも密かな喜びである。その八坂倶楽部の一番奥の座敷からは、綺麗に手入れのされた素晴らしい回遊式庭園を見渡すことが出来る。もちろんこの庭は非公開であり、現在では桜の季節の「都をどり」を観覧される方々に公開されているだけである。

「甲部歌舞練場」の立看板

米国・ニューヨークでの展覧会チラシ
お陰様でフェルメール「光の王国展」も2012年1月に東京・銀座の展覧会施設でスタートを切って以来、今年で4年目を迎えている。初開催の東京・銀座ではかなりの評価をいただき二度に及ぶ会期の延長を果たし、結局その年の11月末までの約350日間におよんだ。その後(第十九回のこのコラムに一部掲載)北海道(旭川)から四国(高知)まで数えること28の会場で順次開催され今日におよんでいる。一方海外でも昨年、オランダ・マウリッツハイス美術館のリニューアル・オープンのPR用CMに「光の王国展」の総合監修役の福岡伸一氏が「光の王国展」での展示作品『真珠の耳飾の少女』を引っさげて登場し、話題になったこともある。しかも、マウリッツハイス美術館の館長からは最高の複製画だと絶賛されている。また今年、新春特別企画として開催された新潟三越百貨店でのフェルメール「光の王国展」のように、連日大盛況で1日の平均入場者数が1,800人を越えた会場もあった。そして、海外では雪の米国・ニューヨークで今年2月下旬のフェルメール「光の王国展」開催の折に、当時42億円で2004年に落札されたフェルメール作品『ヴァージナルの前に座る若い女』の現在の所有者でニューヨーク在住の富豪トム・カプラン氏が祝福に駆けつけている。この4年間、私も各地の展覧会場でディレクターの立場から解説やギャラリー・トークの機会があり、来場された沢山のフェルメールファンと様々な交流の時をいただいた。

会場内の雰囲気
今回の京都・祇園でのフェルメール「光の王国展」は和室での展示である、従来の美術展覧会仕様によるあの厳しい緊張感はなく、何とも言えない和やかな雰囲気の中で、ゆったりと時間が流れて行く。会場では作曲家・久石譲氏による従来のオリジナル楽曲に変わり、著名なバイオリニスト・川井郁子女史の奏でる優雅なオリジナル曲が会場での鑑賞を一層和ませてくれる。そして、最後の作品群が展示されている奥の廊下の向こうには、夕暮れとともに幾つもの照明に照らしだされた庭園が闇の中からその存在感を見事なまでに現わしてくる。そこには和と洋の世界が織りなす独特の安らぎに導かれながら、心地のいい新しい絵画鑑賞に浸れる場が出来上がっていた。
とっぷりと暮れた祇園の街。夕立のあと、そよそよと風が吹き抜ける。真っ赤な団子柄の提灯に送られながら八坂倶楽部の玄関を後にした時、6月20日に日本経済新聞「文化」覧いっぱいに掲載された「複製にはそれ自体固有の価値がある。美術教育の場や文化財保存の手段等にも生かせる。これらの作品を社会的にどう活用して行くかを考える段階に今さしかかっている」と結論づけられた記事が頭の中をよぎった。
Warning: include(/home/admin/public_html/ads_tora.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/031/index.php on line 131
Warning: include(): Failed opening '/home/admin/public_html/ads_tora.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.0.33-3/data/pear') in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/031/index.php on line 131
Warning: include(/home/admin/public_html/right_side.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/031/index.php on line 136
Warning: include(): Failed opening '/home/admin/public_html/right_side.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.0.33-3/data/pear') in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/031/index.php on line 136