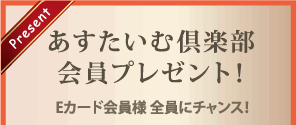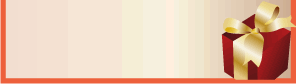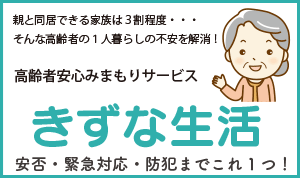![日光の社寺[1999年 文化遺産]](images/world_img_01.gif)
■PROFILE
(財)日光社寺文化財保存会
漆塗り職人
佐藤 則武さん

1949年、山形県に生まれる。塗装の専門学校を卒業後、内装の会社に就職。100年残る仕事がしたくて1972年(財)日光社寺文化財保存会へ。現在は漆塗専門技術主任として、漆塗りだけでなく施工管理から調査研究まで行う。世界遺産に含まれる103棟ほとんどの修復に携わってきた。
■建物の90%に漆が使われている
「日光の社寺」とは、二荒山(ふたらさん)神社、東照宮、輪王寺の建造物群(国宝9棟、重要文化財94棟)と、これらを取り囲む遺跡を指す。徳川家康の霊廟として東照宮が建立されたのは、1617(元和3)年。その20年後、三代将軍家光によって現在ある主要な社殿が造営された。以来、日光では数十年おきに、おもに漆塗り、彩色、錺(かざり)金具を中心とした修理が続けられている。「103棟に上る建造物では、見えている部分の90%以上に漆が使われています」と話すのは、(財)日光社寺文化財保存会で6人の漆塗り職人を束ねる佐藤則武さんだ。見事な金箔や彩色にはつい目を奪われるが、その下にも必ず漆が施されている。
「建物に漆を塗るのには、ふたつの目的があります。まずひとつは、漆には水をはじく効果があるので、雨や直射日光から木を守って長持ちさせるのです。ふたつ目は、接着剤としての役割。下地に漆を塗ってよく磨くことで、金箔や彩色がしっかりつくのです」と佐藤さん。長い年月を経てなお、日光の社寺が威容を保っていられるのは、幾度となく漆を塗り替えてきた成果なのだ。
■仕上げまでに漆を塗ること17回

- 漆を塗り終えた欄間彫刻に金ぱくを押す。若手職人の鈴木晶子さん(左)、若林由理さん(右)とともに
ひと言で漆塗りといっても、日光では保存性を高めるため、仕上げるまでにおよそ40もの作業を要する。まず古い塗りを調べてから、塗膜(とまく)(漆の膜)を叩き落とし、木地を平らにし、ほんの少しのへこみも埋めて、漆を塗っては空研ぎし…、とひたすら地道な作業が続く。全40工程中、漆塗りの回数はなんと17回。また、途中で麻布を下地に着せるほか、麻布のくずである刻苧綿(こくそわた)でくぼみを埋める工法も、日光特有だそうだ。
「麻布を着せるのは木割れを防ぐためです。木割れが起きると、そこから雨水が入って腐りやすくなる。ほかでもやっているかもしれませんが、日光では昔から、雨風の当たるところにはすべて麻布を着せています。刻苧綿を使うのも同じ理由です」。こういった細やかな仕事を、すべての部材に対して行う。気の遠くなるような作業だ。それでも佐藤さんは「毎日毎日、漆塗りできるのが嬉しくてしょうがない。つらいことなどひとつもない」と笑う。生涯かかっても極められないかもしれないが、よい仕事をすれば100年以上残る。その一心でこれまでやってきた。
■古塗膜(ことまく)一片で江戸の職人と対話する

- 漆作業のおもな道具。刻苧綿、地の粉、砥の粉、漆、のみ・かんな類、へら、漆ばけなど
佐藤さんは、中学生だったある旧正月のことを忘れない。最上川上流の山間部にある家で、農業と炭焼きで働きづめだった父親が、窓の外をぼんやり眺めていた。ただそれだけのことだが、父の背中を見て佐藤少年は「いつか親父くらいの歳になったとき、『おれはこれをやってきた』といえるような仕事がしたい」と心に決めた。その気持ちが原点となり、いったんは就職するも、日光で漆職人を求めていると知り、23歳で一から修行を始める。日光の社寺の修理を受託する(財)日光社寺文化財保存会が誕生して数年目のことだった。
「もともと美術が好きだったこともあり、漆の仕事にどんどんのめり込んでいきました。彫刻への理解が深まるよう植物の写生をしたり、自分なりにいろいろ勉強もしました。古い漆がはがれた部分をルーペで観察すると、昔の人の仕事ぶりまでわかるんですよ。『ああ、ここで同じ失敗してるな』とか(笑)。ていねいな仕事も、手を抜いていても、結果がちゃんと残っている」と楽しそうに語る佐藤さんは、たった一片の古塗膜を介して、江戸の職人と対話しているようだ。漆好きが高じて、余暇には蒔絵や螺鈿(らでん)を施した小物を手がける。こちらも日本伝統漆芸展などで入選するほどの腕前だ。「小さい仕事を覚えると、大きな仕事にも生かせるんです。反対に、大きなものばかりやっていると、細かいところまで目がいきとどかない。若い人たちにも、細かい仕事を大切に、といっています」。
漆は、気象条件や材料によって毎回、微妙に塗り方を変えなければならない。また、乾くときに一定の湿度が必要なため、寒さと乾燥の厳しい冬の日光では、とくに苦労がつきものだ。根気のいる仕事だが、幸いにも佐藤さんの後には若手の職人が続く。三男の玄得(ひろやす)さんもそのひとりだ。建物の漆工では珍しい女性の職人も誕生し、佐藤さんは「ようやく漆塗りが市民権を得てきたかな」と感じている。
■失われつつある伝統産業と手を携えて

- 修復中の東照宮透塀(国宝)。左手のあいた部分に、右上の写真で金ぱくを押している欄間彫刻が組み込まれる
現在、日光は2007(平成19)年に始まった「平成の大修理」の真っ最中だ。東照宮の東西透塀(すきべい)、正面唐門、本殿・石の間・拝殿(すべて国宝)をはじめ、着々と修理が進んでいるが、今回の大修理から変わったことがいくつかある。
「以前は、塗りの最後に施す蒔絵は、よその職人に依頼していたんです。それが悔しくて…。必死に蒔絵の勉強をして、今回から私たち地元の職人が手がけられるようになりました。初めて自分たちで蒔絵を施した東照宮唐門は、とくに心に残っています」と佐藤さん。もうひとつ、大きな変化がある。原料の漆そのものだ。
「もともと国産の漆を使っていたのですが、30年前の修理のときは国産が足りず、中国産を使ったんです。それを、今回の大修理から100%国産に切り替えました。国産は、塗るときも乾かすときも難しく、手がかかります。でも建物の外部に塗るには、やはり日本で採れた漆の方が、日本の気候に適していると思います」。場所によって雨や日照の条件が違うので一概にはいえないが、60年前に塗った国産漆が美しいつやと色彩を保っているのに対し、30年前に塗った中国産漆はすでに上塗りがはがれ、その差は歴然としている。
日光で今回から使っているのは、岩手県二戸市浄法寺(じょうぼうじ)産の漆だ。浄法寺では、文化庁が「ふるさと文化財の森システム推進事業」として、漆の原木を育てるとともに、漆掻き技術者を育成している。「いったんは廃れかけた漆掻きですが、いまでは若い人も少しずつ増え、浄法寺地区で30人弱の職人がいます。この浄法寺産の4割くらいを、日光で使っています。中国産に比べると価格は10倍くらいしますが、定期的に購入することで漆掻きが続いていけば、日光も助かります」。
漆だけでなく、文化財を守り伝えるには、それに関わるさまざまな伝統や技術と手を携えなければならない。前述の刻苧綿の原料は、本州で唯一からむし(苧麻)を栽培する福島県昭和村のものだ。また金箔は、工程が大変で職人の減少が進む縁付(えんつき)の打紙(金箔より少し大きい打紙)に貼ったものを使っている。いずれも、伝承が危ぶまれる素晴らしい素材だ。日光の維持・修理に使うことで、それらの継承に少しでも貢献できれば、というのが佐藤さんの願いだ。
「漆は建物の基本なので、あまり評価されないけれど、木を何十年でもじっと守っている。そういうところが好きだなあ」と語る佐藤さんは、日々塗りの技を磨き、いい仕事をすることだけを考えている。国産の材料にこだわるのもそのためだ。取材に訪れた1月半ば、日中も零度を下回る寒さの中、現場には黙々と作業をする人びとの姿があった。佐藤さんはじめ、こういった職人たちの誠実な営みによって「日光の社寺」は連綿と支えられている。
※本内容は日本ユネスコ協会連盟の承諾のもと、転載しています。

このサイトは、プライバシー保護のため、
SSL暗号化通信を採用(導入)しています。
SSL推奨ブラウザについて

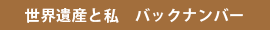
![第5回 日光の社寺[1999年 文化遺産]](images/world_tit_01.jpg)